発足は7年前。アクセサリー等を制作する金属工芸と、花器や竹籠等を制作する竹工芸の職人が、コラボレーションや意見交換をし、人々のニーズにあったものづくりを目指そうとしたのがきっかけだという。それぞれ、技術に長けた職人だけに「ワザ」の追求に走りがちになり、大切なエンドユーザーの意向をおろそかにしかねないという危なっかしさが背景にあった。クラフトセンターをはじめに京都府下での展示・販売会はもちろんのこと、東京は八重洲口にある京都館等でも実績を重ね、ようやく売れるものづくりが可能になってきた。
役員構成は衆長、副衆長、会計の三役で入会資格は特になし。年会費1万円での運営だ。

主な発表の場である「こんちく衆展」を重ねることにより、当初はディスプレイにこりがちだった展示から、お客さまの声を積極的に求める接客に重きをおくようになり、ようやく成果が見えてきたところだ。たとえば白井さんのつくるおりんは、砂張(さはり)という金属を用い、素晴らしく切れのよい、しかもなんとも深い余韻と澄んだ音色を持つ、本物の伝統工芸品である。このおりんを手にしたあるお客さまから、「持ち運べたらいいのにね」という感想を聞くことができた。そこで試行錯誤を重ねて生み出されたのがかわいらしい巾着にすっぽり収まる小振りのおりん、「舞妓りん」だ。みかけは小さいけれど、音色のよさは群を抜く。いやむしろ、見た目がコンパクトなだけに音の良さが引き立つくらいだ。しかもこのルックスのよさ、衆内のアクセサリー作家の作品の横に並べても違和感はないし、何よりもお客さまが実際に音をききたがる。結果、その良さを実感していただけるという効果をもたらした。他のメンバーも接客や商品説明の大切さを学び、今では自然と「こんちく衆ブランド」のようなものが生まれつつある。

こんな楽しい集まりを、どうして補助金も得られない任意団体のままにしておくのだろう? というのはどうやらヤボな疑問のようだ。
本来が伝統工芸に携わる衆のみなさんは、こんちく衆以前に必ず何かの組合や研究会にすでに参加されている方たちばかり。しかも、千年のみやこの伝統だから、堅苦しいことこの上ない。だからココくらいは「良い加減」で気楽な方がいいのだとか。ホームページで情報発信したら? という意見もないではないが、「じゃあ誰が管理するねん?」の問いかけに、「それもそやなあ」とホワーっと消えていく。
たまには堅苦しいことも抜きにして、「気持ちが通じる人たちの集まり」から始めるのもステキなあり方だ。
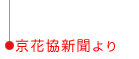


 主な発表の場である「こんちく衆展」を重ねることにより、当初はディスプレイにこりがちだった展示から、お客さまの声を積極的に求める接客に重きをおくようになり、ようやく成果が見えてきたところだ。たとえば白井さんのつくるおりんは、砂張(さはり)という金属を用い、素晴らしく切れのよい、しかもなんとも深い余韻と澄んだ音色を持つ、本物の伝統工芸品である。このおりんを手にしたあるお客さまから、「持ち運べたらいいのにね」という感想を聞くことができた。そこで試行錯誤を重ねて生み出されたのがかわいらしい巾着にすっぽり収まる小振りのおりん、「舞妓りん」だ。みかけは小さいけれど、音色のよさは群を抜く。いやむしろ、見た目がコンパクトなだけに音の良さが引き立つくらいだ。しかもこのルックスのよさ、衆内のアクセサリー作家の作品の横に並べても違和感はないし、何よりもお客さまが実際に音をききたがる。結果、その良さを実感していただけるという効果をもたらした。他のメンバーも接客や商品説明の大切さを学び、今では自然と「こんちく衆ブランド」のようなものが生まれつつある。
主な発表の場である「こんちく衆展」を重ねることにより、当初はディスプレイにこりがちだった展示から、お客さまの声を積極的に求める接客に重きをおくようになり、ようやく成果が見えてきたところだ。たとえば白井さんのつくるおりんは、砂張(さはり)という金属を用い、素晴らしく切れのよい、しかもなんとも深い余韻と澄んだ音色を持つ、本物の伝統工芸品である。このおりんを手にしたあるお客さまから、「持ち運べたらいいのにね」という感想を聞くことができた。そこで試行錯誤を重ねて生み出されたのがかわいらしい巾着にすっぽり収まる小振りのおりん、「舞妓りん」だ。みかけは小さいけれど、音色のよさは群を抜く。いやむしろ、見た目がコンパクトなだけに音の良さが引き立つくらいだ。しかもこのルックスのよさ、衆内のアクセサリー作家の作品の横に並べても違和感はないし、何よりもお客さまが実際に音をききたがる。結果、その良さを実感していただけるという効果をもたらした。他のメンバーも接客や商品説明の大切さを学び、今では自然と「こんちく衆ブランド」のようなものが生まれつつある。